4月の給料は、新社会人になって初めてのお給料ですね!
私も初めてもらった時は、とても嬉しかったのを覚えています。
初任給で両親にうなぎをご馳走しました。
給料は、基本的に金融機関に振込されます。
給料日当日は、入金された金額だけを確認して終わってしまう方が多いようです。ベテラン社員でも、給与明細を確認せずに、入金された金額だけで終わってしまう方も少なくありません。
しかし、給与明細の内容を確認しないと、なぜこの金額が入金されているのか分からなくなってしまいます。
また、数年後に確認した際に、手当として組み込まれていなければならない金額が入っていなかったり、逆に控除しなければいけなかった金額が入っていなかったりした場合、後日、数年分をまとめて徴収される可能性があります。
そうならないように、給与明細をきちんと確認することをおすすめします。
今回、給与明細とはどのようなものかを簡単に説明したいと思います。
給与明細の見方
会社から受け取る給与明細は、オンラインやメールでの確認、または紙での支給となります。
以下に給与明細の例を示して説明しますが、企業によってデザインが異なる場合もあります。ただし、記載されている項目については概ね共通しています。

①支給
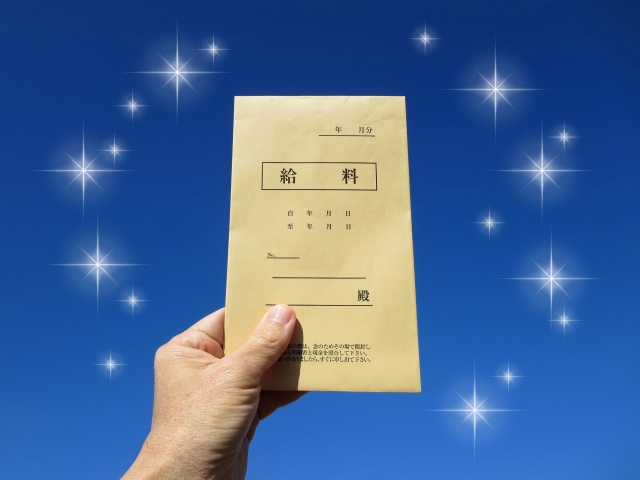
支給欄には、企業があなたに「何を」支払うのか、その項目と金額が記載されます
基本給
企業が従業員に対して支払う給与の基本となる金額です。
- 毎月固定で支払われる:通常、毎月決まった金額が支払われますが、欠勤や遅刻などがあった場合は、その分が差し引かれます。
- 昇給や減給の対象となる:基本給は、従業員の業績や能力、勤続年数などに応じて、昇給や減給の対象となることがあります。
- ボーナス支給額は、基本給を基準に算出されることが一般的です。
- 退職金支給額は、一般的に基本給を基準に算出されます。
役職手当
部長、課長、リーダー(係長、マネージャー、店長など、企業によって異なる役職名)など、役職に就いている従業員に対して、その責任の重さや業務の負担に応じて支給される手当です。
- 一般的に、毎月固定で支払われることが多い。
- ボーナス支給額の算出基準は企業によって異なるが、基本給を基準とする場合が多い。
資格手当
業務に関連する特定の資格を持つ従業員に対して、その資格に応じて支給されます。
【業務に必要な国家資格や民間資格】
例:宅地建物取引士、社会保険労務士、情報処理技術者、介護福祉士などの他、企業が指定する特定の資格
家族手当
多くの企業では、社員の家族構成に応じて支給される手当です。
時間外手当
時間外手当は、法定時間外労働、深夜労働、休日労働などに対して支給される割増賃金の総称です。
※1.時間外手当=残業のうち法定外残業に対して支払われます。
住宅手当
従業員の住宅にかかる費用を補助するために企業から支給される手当で、支給方法は企業によって異なります。
法律で定められたものではありませんので、支給の有無や金額、支給条件は、企業の裁量によって決定されます。
通勤手当
従業員の通勤にかかる費用を補助するために企業から支給される手当です。通勤距離や通勤手段によっては、支給されない場合があります。
通勤手当は、一定額までは非課税ですが、超えた分は給与所得として課税対象となります。
総支給額
税金や社会保険料が差し引かれる前の金額であり、「額面給与」とも呼ばれます。
課税支給額
所得税や住民税などの課税対象となる給与の総額のことです。
非課税支給額
所得税や住民税などの課税対象とならない給与の支給額のことです。
通勤手当や出張旅費、その他、法律で非課税と定められているものが対象です。
控除

ここでは給与明細で控除されている項目の紹介です。
今回、ここでは深くは説明しません。何が控除されているかをご理解いただければいいと思います。
健康保険料
健康保険とは、日本における公的な医療保険制度の1つです。
みんなで少しずつお金(保険料)を出し合い、いざという時(病気や入院など)に医療費の負担を軽くする助け合いの制度です。
日本に住むほとんどの人が、何らかの公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入する義務があります。サラリーマンや公務員などは、主に健康保険に加入します。
健康保険料は事業主と被保険者(加入者)の双方が負担します。
※毎月の給与から控除される健康保険料は、原則として前月分です。しかし、新入社員として4月に入社した場合、4月給与からは保険料は控除されず、最初の保険料は5月給与から控除されることが一般的です。
介護保険料
40歳以上の被保険者が対象で、事業主と被保険者(加入者)の双方が負担します。
卒業したての皆さんには今はあまり関係ないですね。
厚生年金保険料
厚生年金とは、会社などに勤めている人が、老後や万が一の時のために加入する、とても大切な公的な保険制度です。
主に会社員や公務員など、企業や官公庁に勤めている人が加入する公的な年金制度です。 国民年金と合わせて、日本の年金制度の2階部分を構成しています。
厚生年金保険料は、事業主と被保険者(加入者)が折半して支払っています。
※毎月の給与から控除される厚生年金保険料は、原則として前月分です。しかし、新入社員として4月に入社した場合、4月給与からは保険料は控除されず、最初の保険料は5月給与から控除されることが一般的です。
雇用保険料
雇用保険料とは、働く人が失業してしまった場合や、育児休業を取得した場合などに、生活や再就職を支援するための公的な保険制度(雇用保険)を運営するために、事業主と労働者の双方が負担します。
社会保険料合計
社会保険料の合計は、原則として「健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料」に、40歳以上の場合は「介護保険料」を加えた金額になります。
所得税
所得税は、個人の1年間の所得にかかる税金です。毎月の給与からは「源泉徴収」として概算で天引きされます。
年間の所得税額は、年末に会社で行われる「年末調整」で計算され、払いすぎた場合は12月の給与や賞与で返金、不足していた場合は徴収されます。
※会社により、翌年1月以降の給与で調整されることもあります。
年末調整の詳細はこちらでご確認ください。
住民税(市民税)
市民税(住民税)は、住んでいる都道府県・市区町村に納める税金です。
毎月の給与から控除されるのは、前年の所得をもとに計算された年間の税額を分割したものです
新入社員の場合、前年の所得がなければ今年は市民税が発生しないか、少額のことが多いです。
今年働いた分の市民税は、来年から給与から天引きされます。
組合費等
これは、会社の労働組合の運営費(組合費)や、社員の慶弔・福利厚生のための費用(互助会費など)です。
詳細は人事・経理に確認しましょう。
控除合計額
「社会保険料合計+所得税+住民税(市民税)+組合費等+その他」の合計金額です。
差引支給額
「総支給金額-控除合計額」が実際に手元に入る金額です。
まとめ

給与明細には、支給されるお金(支給額)と差し引かれるお金(控除額)が記載されています。
給与明細を受け取ったら、まずは支給額が、入社前に会社から提示された金額と合っているかを確認しましょう。
次に、控除額について疑問点があれば、遠慮せずに人事や経理担当者に問い合わせてください。
給与明細を見て、手取りが思ったより少ないと感じる人もいるかもしれません。しかし、会社員の場合は、自分で納める必要のない社会保険料を会社が代わりに手続きしてくれています。
一方、フリーランスの方は、税金の計算から支払い、納付まですべて自分で行う必要があります。
毎月当たり前のように受け取っている給料も、何が増えて、何が引かれているのかをきちんと確認する習慣をつけましょう。





